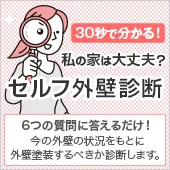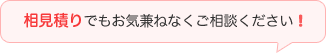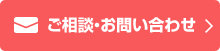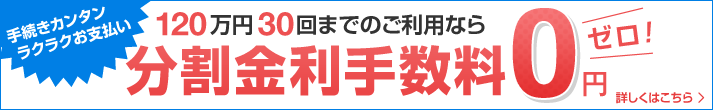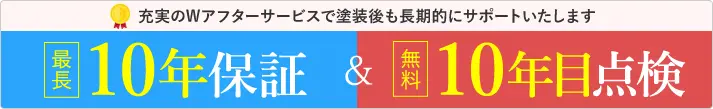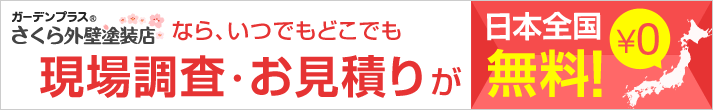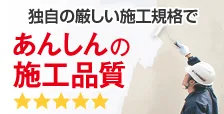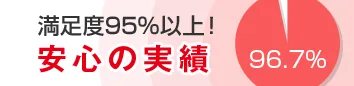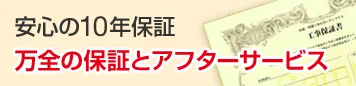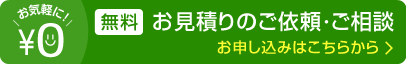外壁塗装の施工ネットワーク
お電話でのご依頼・ご相談 0120-411-807 【受付時間】9:30~17:30
- 営業日カレンダー
-
4月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 5月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 休業日(現場調査・工事は対応)
…休業日(現場調査・工事は対応)休業日もフォームからの問合せ・申込みは可能です。
※各店舗の休業日とは異なります。
-
0120-411-807
【受付時間】9:30~17:30
- お客様コールセンタースタッフ
- 小さなご相談もお気軽にお問合わせ下さい。有資格者が最適な解決策をご提案いたします。
-
-
都
-
小川
-
植松
-
村上
-
森田
-
中野
-
金
-
西村
-
宗行
-
三坂
-
花井
-
須田
-
木村
-
森末
-
濱田
-
織
-
八村
-
田中
-
溜田
-
小嶋
-
嶋
-
石田
-
吉田
-
福本
-
湯本
-
松本
-
吉村
-
上田
-
福井
-
紙谷
-
小林
-
橋本
-
小柴
-
前田
-
森光
-
伊達
-
出田
-
寺口
-
小林
-
石井
-
大西
-
岡田
-
竹内
-
横田
-
佐藤
-
木村
-
福山
-
- メールでのご相談はこちら
- ご利用ガイド
- 塗装実施の目安や劣化症状
- 外壁塗装にまつわるお金
- 外壁の色やデザインの選び方
- 外壁と塗料の種類
- 工事の流れや作業を知る
- 不安要素はこれで解決
- その他
安心セキュリティ
当サイトではFujiSSLのSSL証明書を使用し、常時SSL暗号化通信を行っています。
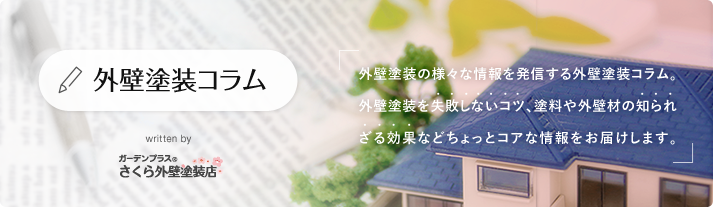
外壁塗装の塗料の種類は?失敗しない選び方・塗料以外の工法も
2025年3月28日更新 2025年3月28日公開
新築後8年から10年程度経つと、外壁の傷みや汚れが気になり始め、デザインを一新したいと思う方が増えます。住んでいる家の外壁デザインや色を考えるのは楽しい作業です。しかし、雰囲気や周囲の環境との兼ね合いや、実際に完成したときのイメージを考えると、どのようなデザインにするか悩む方も多いでしょう。
費用が多額になる外壁工事は、気に入らなくてもすぐに変更することが難しいため、事前にどのような外壁リフォームの方法があるか、知っておくことが大切です。
今回は、多種多様な外壁塗装やリフォームについて、塗料の種類のほか、どのような工法や外壁の模様があるのかを詳しく紹介します。
【種類別】外壁塗装で使う塗料の特徴・グレード
外壁塗装に使われる塗料はさまざまであり、耐用年数や特徴も異なります。
グレードが高いとされる塗料ほど長持ちし、塗り替えの手間が省ける一方で、基本的に1m2あたりの料金は高くなるのが特徴です。
以下では、外壁塗装で使う各塗料の特徴や費用、耐用年数について解説します。
アクリル塗料
アクリル塗料は、アクリル樹脂を主成分とする、1950年代頃から普及しはじめた歴史ある塗料です。現在はウレタン塗料やシリコン塗料など、より耐久性に優れた製品の登場により主流からは外れています。しかし、「低価格で手軽に塗装できる」「発色がよくカラーバリエーションが豊富」という魅力があるため、依然として一定の需要があります。
アクリル塗料のメリットは、塗料単価が安いことです。一般的に1m2あたり1,000~1,800円ほどとされており、同面積でもウレタンやシリコンより低コストに抑えられます。
また、ツヤや発色のよさにも定評があり、豊富なカラーバリエーションの中から好みの色を選択できる点も魅力です。DIY向けの製品も多く販売されており、自分で塗り替えをしたい方にも向きます。
一方で、アクリル塗料の耐久年数は3~8年程度と短く、紫外線の影響を受けやすいことからチョーキングやひび割れ(クラック)が生じやすい欠点があります。外壁や屋根の塗装では足場代などの付帯費用が必要になるため、塗り替えサイクルが短いほどトータルコストが高くなりがちです。
そのため、「長く住むマイホームをしっかり守りたい」という場合にはあまりおすすめできません。また、防汚性の面でも、より上位グレードの塗料と比べると劣る傾向があります。
犬小屋や自宅の倉庫など、塗り替えが簡単で耐久性をさほど必要としない建物をDIYで塗り替える場合、アクリル塗料は向いていると言えます。
| 耐用年数 | 約3~8年 |
| 相場価格 | 約1,000~1,800円/m2 |
| メリット | ・コストを抑えられる
・発色がよい |
| デメリット | ・耐久性が低い
・防汚性が低い ・紫外線の影響を受けやすい |
ウレタン塗料
ウレタン塗料は、ウレタン系樹脂を主成分とした塗料です。現在はより耐久性の高いシリコン塗料が外壁塗装には主に使用される一方で、弾力や密着性が高く、比較的低コストという特徴があることから、今も一定の需要があります。
ウレタン塗料の価格帯はアクリル塗料よりは上、シリコン塗料よりは下で、工事費用の目安としては1m2あたり1,500~2,500円程度が相場です。また、塗膜の柔軟性が高いため、外壁やベランダなどにひび割れが生じても追従しやすく、下地の動きによるひび割れを抑制してくれます。加えて、ツヤ感や発色性も優れており、高級感のある仕上がりを求める方にも向いています。
一方、デメリットは耐久年数が5~10年程度とやや短めで、紫外線による劣化や黄ばみが起こりやすい点にあります。長く住む家の外壁を一度にしっかり守りたいという場合は、シリコン塗料やラジカル制御型塗料など、より耐久性に優れた種類を検討したほうが長期コストを抑えやすいでしょう。
また、溶剤系のウレタン塗料は施工時の溶剤臭が強く、屋外でも隣家への配慮が必要です。
総じてウレタン塗料は、コスト重視で塗装をしたい人や、弾性を生かしてひび割れを抑えたい場所、あるいはベランダ防水など部分的に使用する際に適した塗料と言えます。
| 耐用年数 | 約5~10年 |
| 相場価格 | 約1,500~2,500円/m2 |
| メリット | ・比較的ローコストで塗装できる
・塗膜の柔軟性が高くひび割れしにくい ・ツヤ感や発色性に優れる |
| デメリット | ・耐久年数が短めである
・紫外線で劣化や変色を起こしやすい ・一部の製品は施工時に強いニオイを発生させる |
シリコン塗料
シリコン塗料は、シリコン系合成樹脂を主成分とする塗料です。日本の戸建て外壁塗装において最もスタンダードと言われる塗料で、価格・耐久性・機能性のバランスがよい特徴があります。
シリコン塗料の耐用年数は一般的に8~10年程度で、アクリル塗料やウレタン塗料より長く、フッ素塗料や無機塗料よりはやや短いレンジです。1m2あたりの価格相場は2,000~3,500円とフッ素塗料や無機塗料と比べて低価格であり、コストパフォーマンスが高い点が強みです。定期的な塗り替えの手間やトータル費用を減らしながら、塗り替え金額が高くなりすぎない塗料と言えます。
また、塗膜表面が撥水性を持つため、雨水でホコリや泥が洗い流されやすいという特徴があります。湿気によるカビ・苔の発生も抑えられ、美観を長期間キープしやすい点もメリットです。光沢が長持ちし、仕上がりが美しく仕上がるほか、市場でのシェアが高い塗料なだけに、各塗料メーカーからさまざまなカラーバリエーションや遮熱・断熱機能を持つ製品も出ています。
一方で、シリコン塗料は塗膜が比較的硬いぶん、モルタル壁など動きやすい素材にはひび割れが生じやすい傾向があります。また、撥水性が高いぶん、シリコン塗膜の上にさらに塗料を塗り重ねる場合、適切な下地処理が必要です。DIYにはやや扱いにくいこともあり、実績のあるプロに任せたほうが安心です。
| 耐用年数 | 約8~10年 |
| 相場価格 | 約2,000~3,500円/m2 |
| メリット | ・コストパフォーマンスのバランスがよい
・撥水性や防汚性、防カビ性能が高い |
| デメリット | ・ひび割れやすい
・塗り重ねが難しい |
ラジカル制御型塗料
ラジカル制御型塗料とは、塗膜の劣化要因となるラジカルの発生や拡散を抑え、塗料の寿命を約12~15年と大幅に延ばす技術を採用した塗料です。
ラジカルとは、塗料の白色顔料として必須の酸化チタンが、紫外線に触れた際に発生させるエネルギーのことです。ラジカル制御型塗料はラジカルを閉じ込め、漏れ出したラジカルを補足する仕組みにより、塗膜劣化を防ぎ、退色やチョーキングを抑えています。
ラジカル制御型塗料の価格帯は、1m2あたり約2,300~3,500円程度と、シリコン塗料と比べると高めな一方、フッ素塗料や無機塗料ほど高くはありません。また、ラジカル制御型塗料はラジカルを封じ込めるため、チョーキングが起こりにくく、長期にわたって美観を保ちやすい強みがあります。
親水性や撥水性に配慮した製品も多く、雨水によってホコリや汚れが洗い流されやすくなっています。また、比較的光沢が強い仕上がりになりやすいのも魅力の1つです。
一方で、ラジカル制御型塗料は近年登場した製品で、シリコンやフッ素などの従来塗料より販売実績が少なめです。大手メーカーの暴露試験などで性能は証明されているものの、実際の施工事例が少ない点に不安を感じる方もいます。
また、ラジカル制御の要である酸化チタンは白色顔料のため、濃い色を調合しづらいケースがあります。製品によっては色の選択肢が制限される場合もあるので、事前に業者に確認すると安心です。
| 耐用年数 | 約12~15年 |
| 相場価格 | 約2,300~3,500円/m2 |
| メリット | ・耐候性や耐久性が高くコスパがよい ・チョーキングが起きにくい・親水性や撥水性にすぐれた製品も多い |
| デメリット | ・歴史が浅く販売実績が少ない
・濃彩色の再現が難しい場合がある |
光触媒塗料
光触媒塗料は、酸化チタンなどの成分が紫外線に反応して有機汚れを分解し、雨水で洗い流す「セルフクリーニング機能」を持つ高性能塗料です。光触媒塗料はメーカー公表値として15~20年程度の耐久性がうたわれることが多く、一般的なシリコン塗料より長寿命です。
また、光触媒の作用により、カビや藻などの微生物も分解・抑制されやすいほか、一部製品では排気ガスなどの有害物質(NOx)を分解する機能があります。大気汚染による汚れを防ぎ、周辺の空気をきれいにする効果も期待できます。
一方で、光触媒塗料の施工単価は、1m2あたり3,800~5,000円程度が一般的とされ、シリコン塗料の約1.5倍~2倍ほど高価です。例として、延床30坪ほどの住宅外壁を全面塗装する場合、費用が100万円以上になることも珍しくありません。
また、紫外線が当たらない部分や雨水が十分にかからない場所ではセルフクリーニング効果が十分発揮されず、汚れの分解が進みにくい場合があります。その結果、想定より早く経年劣化が進むケースもあるため、必ずしもカタログ値通りに長持ちするとは限りません。
加えて、酸化チタンが白色顔料であるため、濃い色味や鮮やかな色の再現が難しい場合もあります。デザインの自由度が低くなるケースもあるでしょう。
総じて光触媒塗料は、汚れに強く、美観を長く保てる塗料を探している方には魅力的な選択肢です。ただし、日当たりや雨水の当たり方によって効果が落ちるケースもあるため、自宅に向いているか施工業者と相談した上で使用するかどうか決めるのがおすすめです。
| 耐用年数 | 約15~20年 |
| 相場価格 | 約3,800~5,000円/m2 |
| メリット | ・紫外線に反応して汚れやカビを自動的に分解する ・耐久性や耐候性にすぐれる |
| デメリット | ・値段が高い
・場所によってはセルフクリーニング効果が発揮されない ・濃彩色の再現が難しい場合がある |
5分でわかる!光触媒塗料を外壁塗装に使うメリットとデメリットについて
ナノテクノロジー塗料
ナノテクノロジー塗料は、塗料の主成分となる樹脂をナノレベルのサイズまで小さくする技術を取り入れた新型塗料です。
塗膜内に超微粒子シリカが均一に分散することで、外壁表面に汚れが侵入しにくくなります。さらに親水性が高いため、雨水で汚れが浮き上がり、自然に洗い流されるセルフクリーニング効果が期待できます。そのため、耐用年数はおおむね10~16年程度とシリコン塗料やラジカル制御型塗料と同等かやや上のレンジです。
また、塗膜表面の有機成分が燃焼した場合でも、下層の無機質成分と融合した膜が酸素の侵入を遮断し、延焼を抑制する効果があります。加えて、従来の水性・溶剤系塗料と比べ、樹脂の使用量が大きく削減されており、製造・廃棄時のCO2排出量を抑えられます。環境に配慮した選択肢を求める方にとっても魅力的でしょう。
一方で、シリコン塗料などと比較すると1m2あたりの価格相場が約2,300~4,500円とやや高額になるため、初期費用としては負担が大きくなります。長期的なメンテナンスコストとのバランスを十分に検討しましょう。加えて、光触媒塗料と同様に雨水で汚れを流す仕組みのため、日陰や雨が当たらない部分では汚れが残りやすくなる恐れがあります。セルフクリーニング任せにはできず、定期的なメンテナンスが必要になる点には注意が必要です。
総じて、長期的に外壁をきれいに保ちたい、環境に配慮した家を建てたい方におすすめの塗料です。ただし、塗装面積や建物環境によってはほかの塗料のほうがコスパに優れる場合もあります。
| 耐用年数 | 約10~16年 |
| 相場価格 | 約2,300~4,500円/m2 |
| メリット | ・汚れに強くセルフクリーニング効果がある ・難燃性で火災に強い・環境負荷が小さい |
| デメリット | ・価格帯が高めに設定されている
・雨が当たらない場所では汚れが残りやすくなる |
ピュアアクリル塗料
ピュアアクリル塗料は、一般的なアクリル塗料に含まれる不純物をできるだけ取り除き、アクリル本来の性能を最大限に引き出した高耐久タイプの塗料です。
ピュアアクリル塗料の耐用年数は約15~20年であり、耐久力の高いフッ素塗料と同等レベルとされます。紫外線に強い大きめのアクリル分子を使用するため、特に耐光性や耐熱性に優れており、チョーキングや退色が起きづらい点がメリットです。
また、塗膜がゴムのように伸びるため、外壁に発生したひび割れにも追随し、防水性能を長期にわたって保持できます。水の侵入を防ぎ、雨漏りリスクや下地の劣化を抑制する点も強みです。
一方で、弾性が高いぶん、塗膜表面がゴム状になりやすく、ホコリや排気ガスなどの汚れを吸着しがちな点はデメリットです。定期的な外壁の洗浄や点検が必要になるケースもあるでしょう。また、弾力があるため、下地に水分が入り込むと温度変化で塗膜が押し上げられ、水膨れのように「膨れ」を起こしたり、剥離が起こったりするときがあります。
加えて、1m2あたりの施工単価は2,800~3,800円程度と、シリコン塗料よりも高めです。延床30坪ほどの一般的な住宅を全面塗り替えする場合、足場代などの諸費用も含めると、100万~120万円ほどになる可能性もあります。長期使用を想定している場合は検討の価値がありますが、短期的なコストを抑えたい方には不向きです。
| 耐用年数 | 約15~20年 |
| 相場価格 | 約2,800~3,800円/m2 |
| メリット | ・耐久性が高い
・高い弾性と防水性がある |
| デメリット | ・汚れやすい
・下地に水分が入ると塗膜が膨れたり剥がれたりする ・費用がかかりやすい |
フッ素塗料
フッ素塗料は、フッ素樹脂を主成分とする塗料で、紫外線や雨風にさらされても劣化しづらい耐久性・耐候性が強みです。一般的にフッ素塗料の耐用年数は約12~14年で、上位グレードの無機塗料に次ぐ高い耐久性を誇ります。立地環境や施工品質によっては15年以上機能を維持するケースもあり、塗り替えサイクルが減らせるため、長期的なメンテナンスコストを抑えたい方には大きなメリットとなります。
また、塗膜の劣化が少ないため、チョーキング(粉化)や変色が起きにくく、さらに表面が親水性を持つことから雨が降ればホコリや排気ガスの汚れが洗い流されます。加えて、シリコン塗料などと比べても光沢保持率が高く、新築時に近いツヤを長期間楽しめるのが魅力です。さらに、塗膜が硬く、藻やカビの発生を抑える力を持つ商品も多いため、湿気の多い地域や日陰が多い立地でも効果を発揮します。
一方で、フッ素塗料の費用相場は1m2あたり約3,500~5,500円で、シリコン塗料に比べると施工単価が1.5倍程度になる場合があります。一度の出費としては大きくなるため、短期的な予算に余裕がない場合は導入しづらいでしょう。
また、弾力性が低いため、モルタル外壁のように動きやすい下地では小さなクラックが発生しがちです。弾性タイプのフッ素塗料を選ぶなどの対策が必要なケースもあります。
また、フッ素塗料は表面が硬く、親水性が高いので、次回の塗り替え時には密着性を高める特殊な下塗り材が必要になることがあります。塗装難易度が高いため、フッ素塗料を使った塗装実績が十分にある業者を選ぶのが大切です。
| 耐用年数 | 約12~14年 |
| 相場価格 | 約3,500~5,500円/m2 |
| メリット | ・耐久性や耐候性が高い
・親水性が高く汚れが落ちやすい |
| デメリット | ・施工費用が高くなりやすい
・弾力性が低くひび割れやすい ・塗装難易度が高い |
無機塗料
無機塗料は、セラミックやケイ素などの無機物を主成分として含んだ塗料です。紫外線にさらされても劣化しにくいという性質があり、約15~20年と現在流通している外壁用塗料の中でも最上位クラスの長寿命を持ちます。
また、カビやコケのエサとなる有機物の含有量が少ない上、塗料自体の親水性も高く静電気も帯びにくいのが特徴です。カビやコケが生えず、埃や排ガスなどで壁に汚れが付きにくいため、長期間にわたって美観を維持できます。
さらに、無機物は原則として燃えにくい性質を持つため、火災が起きた際のリスクを減らせる点も魅力です。
一方で、無機塗料の施工費用は1m2あたり5,000~5,500円程度が一般的で、他の塗料と比べて単価が高く、一度にまとまった費用が必要です。初期投資の負担が大きいため、短期的な予算重視の方には不向きとなる可能性があります。
また、無機塗料は塗膜が硬く弾性に乏しいため、外壁自体にクラックが入った場合、一緒に割れてしまうケースもゼロではありません。モルタル外壁のように動きやすい下地では特に注意が必要です。
さらに、無機塗料の表面は親水性が高く汚れを弾きやすい反面、上塗りするときに塗料が密着しづらい特徴があります。高性能な分、適切な下地処理や規定の塗布量を守るなど、職人の施工精度が仕上がりに大きく影響するため、無機塗料の施工実績が豊富な業者を選ぶことが重要です。
| 耐用年数 | 約15~20年 |
| 相場価格 | 約5,000~5,500円/m2 |
| メリット | ・既存の塗料の中でも耐久性が最も高い ・カビやコケが生えにくく汚れも落としやすい・難燃性で火災リスクを減らせる |
| デメリット | ・施工費用が高い
・硬い分クラックが発生しやすい ・塗装難易度が高い |
外壁塗装で使う塗料で押さえたいポイント
外壁塗装で使う塗料には、「水性」「油性」、「1液型」「2液型」など、さまざまな種類があります。塗料を選ぶ際には、事前にそれぞれの違いについて理解した上で検討するのが大切です。
水性塗料と油性塗料の違い
外壁塗装に用いる塗料は、水で希釈する水性塗料と、シンナーなど有機溶剤で希釈する油性塗料に大別されます。それぞれにメリット・デメリットがあり、用途に応じた選択が重要です。
| ・水性塗料
刺激臭が少なく環境や人体への影響が小さい上、用具を水洗いでき後片付けが容易なのがメリットです。一方で金属面への密着が弱く、低温時に乾きにくい場合があるなど、耐久性面で油性塗料に劣る点がデメリットです。 ・油性塗料 塗膜が硬く乾燥も早いため耐久性が高い点がメリットです。反面、シンナー由来の臭いが強く、道具の洗浄にもシンナーを要するなど取り扱いに注意が必要なのがデメリットです。 |
技術の進歩により、現在の水性塗料は耐久性の面でも油性塗料に引けを取らない製品が増えています。
そのため、特に住宅外壁の塗り替えでは、近隣への配慮から水性塗料が主流です。ただし、耐久性を特に重視する場合は油性塗料が選ばれることもあります。
1液型と2液型の違い
塗料は、缶の中で完結している1液型と、主剤と硬化剤を混ぜて使用する2液型に分かれます。
| ・1液型塗料
硬化剤を混ぜる必要がなく作業が簡単で、余った塗料を保存できるなど扱いやすいのがメリットです。同じ塗料の2液型に比べ価格もやや安価ですが、塗膜の耐久性は劣り、外壁を保護できる期間が短くなる点がデメリットです。 ・2液型塗料 主剤と硬化剤を使う直前に混ぜ合わせるため扱いが難しい反面、塗膜が強力に硬化して耐久性が高いのが特徴です。適切に混合すれば長期間外壁を守れるためプロの現場では高耐久を要する場合に採用されますが、価格が高めで一度混ぜると使い切らないと固まるなど取り扱いが難しい点がデメリットです。 |
一般的な戸建て住宅の外壁塗り替えであれば1液型でも十分対応できます。ただし、耐久性をより高めたい場合は、2液型を使った施工がされます。
艶ありと艶なしの違い
塗料の仕上がりには、艶ありと艶なし(艶消し)の2種類があります。艶の有無で外壁の見た目が大きく変わり、耐久性や汚れの付きにくさにも違いが出るため、希望の外観に合ったほうを選びましょう。
| ・艶あり
外壁に光沢が出て明るく高級感のある仕上がりになるのがメリットです。塗膜表面が滑らかで雨水による汚れが流れ落ちやすく、紫外線にも強いため耐久性にも優れます。一方、光の反射で壁の凹凸が目立ちやすく、和風住宅など落ち着いた雰囲気には不向きな場合がある点がデメリットです。 ・艶なし 落ち着いたマットな質感となり、光沢を抑えたい場合や和風の建物に適しています。壁面の細かな傷や凹凸も目立ちにくいメリットがあります。ただし、表面に微細な凹凸があるぶんホコリや汚れが付着しやすく、艶ありに比べて耐久性がやや劣る点がデメリットです。 |
また、塗料によっては完全な艶消しからフル艶まで段階的に調整できる製品もあります。
失敗しない!外壁塗装の塗料の選び方
外壁塗装に使われる塗料を選ぶ際には、「どのような素材の壁に塗るのか」「塗料にどういった性能を求めるのか」をしっかり考えることが重要です。ここでは外壁材との相性と塗料の性能・機能という2つの観点から、塗料の選び方を紹介します。
外壁材との相性
外壁の種類ごとに向いている塗料は、以下の通りです。
| サイディング外壁 |
| サイディング外壁には、シリコン系塗料やラジカル制御型塗料などの透湿性(湿気を通す性能)が高い塗料が向いています。
多くの戸建て住宅に採用されている、一般的な窯業系サイディングボードはセメント系の板材です。サイディング自体に防水性はなく、表面の塗装によって雨水の侵入を防いでいます。したがって、サイディング外壁には、透湿性が高い塗料が適しています。 透湿性の高い塗料であれば、万一壁内部に水分が入り込んでも水蒸気を塗膜の外に逃がすことができ、塗膜の膨れや剥がれを防ぐことが可能です。 |
| モルタル外壁 |
| モルタル外壁は細かなひびが発生しやすいため、ピュアアクリル塗料などの伸縮性の高い弾性塗料が向いています。弾性塗料なら、モルタルに細かなひびが入っても塗膜がゴムのように伸びて沿うため、ひび割れ部分から雨水が入りにくくなります。
またモルタル壁は吸水性が高く、塗膜に透湿性がないと万が一内部に入った湿気がこもってしまうため、防水性と同時に透湿性も兼ね備えた塗料だとなお安心です。一般に水性塗料は油性に比べ透湿度が高い傾向があるため、水性塗料を選ぶのがおすすめです。 |
| ALC外壁 |
| ALCは多孔質で吸水性が高く、塗膜に隙間ができると、そこから雨水を盛大に吸い込んでしまいます。シリコン系塗料やフッ素系塗料の中でも、高い防水性と透湿性を持つ塗料を選ぶとよいでしょう。
またALCは断熱性能が高い反面、蓄熱しにくいので夏場の遮熱効果はさほど必要ありません。それよりも防カビ・防藻性能を持つ塗料を選ぶと、湿気が関与するトラブルを防ぎやすくなります。 |
| 木材外壁 |
| 板張り外壁やウッドサイディングなど木材を使った外壁は、吸水・放湿による膨張収縮が大きく、また紫外線や雨水にさらされると劣化しやすい素材です。
ウレタン樹脂塗料は耐久性が高く木の伸縮に対応する弾性も持ち合わせていることから、屋内外の木部に昔から広く用いられる定番塗料です。一方で、木材は素材自体が呼吸しているため、通気を完全に遮ってしまうような塗料は向いていません。 |
塗料の性能・機能
外壁塗料には、さまざまな機能性を持った製品があります。耐久年数だけでなく、「どういった環境でどのような効果を発揮する塗料か」を理解しておくと、自宅に合った製品を選びやすくなります。代表的な塗料の機能は、以下の通りです。
| 耐候性 | 塗膜が雨風や紫外線に耐えて劣化しにくい性質です。耐候性が高い塗料ほど色あせやチョーキングが起こりにくく、長期間にわたり性能を保ちます。 |
| 防水性 | 塗膜が水を通さず雨水の侵入を防ぐ性能です。ひび割れがない限り塗膜自体が壁への防水層となります。防水性の高い塗料はモルタルやALCのような吸水性の高い壁材に必須で、雨水による構造体の腐食やカビ発生を防ぎます。 |
| 低汚染性 | 汚れが付着しにくく、付いても雨で流れ落ちやすい性質です。外壁の美観を長く保つのに役立ちます。親水性が高い塗料は雨水が汚れの下に入り込み、洗い流す効果があります。また帯電防止効果がある塗料は埃を寄せ付けません。 |
| 遮熱性 | 太陽光の赤外線を反射し、塗膜や壁の温度上昇を抑える性能です。真夏の強い日差しを受けると、通常の濃色塗膜では壁面温度が非常に高くなりますが、遮熱塗料を使うと表面温度を大幅に低減できます。断熱塗料と違い、保温効果はありません。 |
| 断熱性 | 熱を通しにくい塗膜を形成する性能です。遮熱が「外からの熱を反射する」能力なのに対し、断熱は「壁を伝わる熱エネルギーそのものを伝えにくくする」能力と言えます。夏は外の熱が室内に伝わりにくく、冬は室内の暖気が外に逃げにくくなる効果があります。 |
| その他の性能 | ほかにも、塗料には防カビ・防藻性、難燃性、光触媒機能などさまざまな機能があります。 |
住環境によっては、以下のような機能があると安心です。
| 寒冷地 | 水分の凍結によりひび割れにくい、弾力性・防水性・耐候性の高い塗料 |
| 温暖多湿な地域 | 湿気でもカビが生えない防水性と防カビ・防藻性が高く、かつ遮熱性の高い塗料 |
| 海沿いの地域 | 塩害による劣化を防げる、耐候性・耐久性の高い塗料 |
現在の外壁の雰囲気を残すには?
外壁塗装のやり方によっては、長く過ごしてきた我が家をそのままの形で残したいという要望に応えることも可能です。
| ・クリア塗料で塗装する
クリア塗料は無色透明な塗料です。クリア塗料で外壁をコーティングすることで耐水性が高くなり、建物の耐久性を上げられます。コンクリート打ち放しの外壁や、塗装されている外壁をそのままの色合いで残しながら、耐用年数を伸ばすことも可能です。 ・同じ色・同じ塗料で塗装する 以前使った塗料と同じ色を重ねれば、外壁を新調しながら、現在のまま外見を再現できます。クリア塗料よりも高機能な塗料が多いので、実用性の点でもおすすめの方法です。 |
外壁リフォームの主な選択肢は「外壁塗装」と「サイディング」
外壁のリフォーム方法としては、大きく分けると塗料を使った外壁塗装と、サイディングを取り付ける方法があります。
もっともスタンダードな施工は、塗料を使った塗装で、多彩な色合いと質感が魅力です。
塗料の色や質感は多様で、ツヤ感のあるものとマットなものとでは完成した時の雰囲気も変わってきます。光沢がある方が艶々として強いインパクトがあり、光沢無しは反対に落ち着いてシックな印象を与えます。
さまざまな住宅の外壁を観察し、カラーだけではなく光沢についても検討しておきましょう。
また、塗料の中には大理石や御影石、陶器などの素材を混ぜることで独特の質感を表現する製品もあります。特に大理石や御影石が含まれる塗料は塗るだけで外壁が石で出来ているかのような重厚で高級感溢れる仕上がりになる上、実際に石材を使用した外壁よりもリーズナブルな価格で施工ができます。
通常、塗料だけだとどうしてものっぺりとした印象になりがちですが、こうした特殊な塗料は繊細な質感があるのでワンランク上の仕上がりになるでしょう。
外壁リフォームの主な選択肢は「外壁塗装」と「サイディング」
外壁のリフォーム方法としては、大きく分けると塗料を使った外壁塗装と、サイディングを取り付ける方法があります。
もっともスタンダードな施工は、塗料を使った塗装で、多彩な色合いと質感が魅力です。
塗料の色や質感は多様で、ツヤ感のあるものとマットなものとでは完成した時の雰囲気も変わってきます。光沢がある方が艶々として強いインパクトがあり、光沢無しは反対に落ち着いてシックな印象を与えます。
さまざまな住宅の外壁を観察し、カラーだけではなく光沢についても検討しておきましょう。
また、塗料の中には大理石や御影石、陶器などの素材を混ぜることで独特の質感を表現する製品もあります。特に大理石や御影石が含まれる塗料は塗るだけで外壁が石で出来ているかのような重厚で高級感溢れる仕上がりになる上、実際に石材を使用した外壁よりもリーズナブルな価格で施工ができます。
通常、塗料だけだとどうしてものっぺりとした印象になりがちですが、こうした特殊な塗料は繊細な質感があるのでワンランク上の仕上がりになるでしょう。
サイディング工法とは?種類や模様はどのようなものがある?
サイディングとは、外壁に張る仕上げ用の板材のことです。モルタル壁とは違い、パネル状の壁材を貼り合わせて施工します。
主流のサイディングには、以下のような種類があります。
| ・窯業サイディング
窯業サイディングは、セメントや繊維質などを主原料に板状に成形し、高温・高圧または蒸気養生などで硬化させた外壁材です。多くはレンガや石材のような模様が施されています。実際のレンガや石を用いるより安価に、レンガや石材のような模様を作れるコストパフォーマンスのよさから、日本国内では約8割の住宅でシェアされているサイディング材です。 ・金属系サイディング 金属系のサイディング材は金属をそのまま外壁に用いる工法で、独特の模様や質感がスタイリッシュで未来的なイメージを演出できます。新築では窯業サイディングの次に普及しているサイディング工法です。 ・木目風・タイル風サイディング 木質の柔らかさ、ぬくもり感を外壁に生かしたサイディング材は、木の家のような温かな雰囲気を醸し出すことから人気の高いサイディング模様の1つです。タイルやレンガ模様のサイディングもあります。実際に木やレンガで外壁施工をするには工費や材料費が高くなりますが、サイディングであれば見た目が本物の素材のような模様でありながら、リーズナブルで丈夫であるというメリットがあります。 |
そのほかにもさまざまな模様のサイディングがあるので、施工業者に相談してみましょう。
好みの模様にできる!外壁塗装の工法
外壁塗装工事には、塗料を外壁に塗るだけではなく、さまざまな工法があります。職人の腕や経験が必要になる工法もありますが、施工業者に相談すれば、好みの模様や雰囲気に仕上げることができます。
塗料での外壁塗装以外の工法を紹介します。
外壁塗装の工法① 漆喰 (しっくい)
漆喰は、日本では馴染み深く、古くから家屋や城郭に使われている素材です。厚みのある塗膜により立体的な模様が付けられることが特徴です。
コテやローラーを使って模様をつけていくので、職人の技術や経験が必要であり、高級感溢れる模様作りには手間がかかります。ランダムな模様やレンガ模様、波型のように幾何学的な模様も付けられます。
漆喰は手作業の温かさが残る素朴で穏やかな風合いが人気で、伝統的な外壁だけでなくレストランなどの内装にも用いられています。
漆喰は呼吸する壁と言われ、調湿性・消臭性・安全性・抗菌性・不燃性などのメリットがありますが、手作業のため仕上がりまでに時間がかかるというデメリットもあります。
外壁塗装の工法② 吹き付け工法
吹き付け工法とは、中に骨材という粒子を含む塗料をスプレー吹き付けすることにより独特な模様をつける工法です。吹き付け工法は立体的な模様をつけることができ、レトロな雰囲気を好む人に選ばれています。
吹き付け工法には、以下のような種類があります。
| ・リシン仕上げ
骨材が混ぜ込まれた塗料を使用し、表面が細かい砂のようにざらざらとした外観になる塗装方法です。和風住宅に用いられることが多く、意匠性が高いデザインに仕上がります。耐用年数は8年程度です。凸凹があるため埃や水垢が溜まりやすく汚れやすいデメリットがあるほか、防カビ・防藻機能はないので湿気が多い場所は注意が必要です。 ・スタッコ仕上げ 合成樹脂にセメントや骨材などを混ぜた原料を使用し塗装する方法で、仕上がりは凸凹のある意匠性の高い仕上がりになります。耐用年数は8年から10年ほどと比較的長いでしょう。スタッコ仕上げはリシン仕上げより模様が大きく塗膜が厚めです。 ・吹付けタイル タイルのようにつるつるとした陶磁器調の仕上がりにする方法です。汚れが落ちやすく、塗膜に厚みがあり耐用年数が10年から15年と比較的長めです。 |
ステンシルシール工法
ステンシルシール工法とは、外壁にステンシル(型抜き)で模様をつける工法で、外壁全体を塗装する工法ではなく、外壁の一部に施工するものです。
施工方法としては、模様のついたステンシルシールを外壁に貼りつけた上から塗装をしながら描いていきます。さまざまな模様がありますが、特に蔦や花といった植物、ステッチ模様のような図案に人気があります。
施工できる業者は限られるので、検討している場合はあらかじめ業者に施工できるか確認しておくとよいでしょう。
外壁塗装や外壁工事をする際のポイント
外壁塗装や工法をする上で、おしゃれに演出したり、ほかの家とは違った雰囲気を醸し出したりするためには、カラーや質感を複数組み合わせるのがおすすめです。
例えば、1階と2階を別のカラーにしたり、外壁の角だけ・ベランダだけを違う色にすると魅力的でスタイリッシュな雰囲気になるでしょう。また、質感の違う塗料を組み合わせることで、見た目の印象が変わり高級感も演出できます。
住宅の形や、外観の見え方などは、外壁塗装業者の専門家に相談することをおすすめします。
「考えていたイメージと違った」を防ぐには?
外壁工事はかかる費用が大きいため、簡単にやり直しをすることが難しい工事です。
実際に施工したらイメージと違ったという事態にならないためにも、以下のようなポイントを押さえておきましょう。
カラーシミュレーターでよくイメージする
カラーコーディネートを考える時には、頭の中でイメージするだけではなく、カラーシミュレーターを使って実際のカラーリングを目で見て確認することが大切です。
外壁塗装業者のホームページや店舗にあるカラーシミュレーターで雰囲気やバランスをよく確認しましょう。カラーパレットや色見本を見るだけでは分からない具体的なイメージが確認できます。
施工例をたくさん見る
業者を選ぶ際に、写真で掲載されている過去の施工実績を確認して参考にしましょう。お住まいのイメージが近い、もしくは同じ塗料の使用実績があるなら、その業者に依頼した場合の参考になります。
お住まいの住居の形や、使いたい配色など施工例からイメージを探すのも有効です。
完成のイメージを業者に作ってもらう
多くの塗装業者が、認識合わせのために外壁塗装が完成した時のイメージを作るサービスを行っています。もし、利用する業者にそういったサービスがあれば利用してみましょう。
具体的なイメージがあると、さらに希望やこだわりを反映させることが可能です。
希望の外壁塗装や工法を扱っている業者か確認することも大切!
希望のデザインや使いたい模様のサイディングを、依頼したい業者が扱っていなければ工事をしてもらうことはできません。また、職人の技術や経験、施工実績は完成度を大きく左右します。
職人の技術力や経験は消費者には知りえないことかもしれませんが、判断する方法としては、以下が挙げられます。
| ・施工例を多く挙げているか/実績は豊富かチェックする
・複数の業者に相談する ・気になることや心配なことに対してきちんとした回答を得られるか、回答が迅速であるか確かめる |
少しでも納得のいかないことがあれば、その後も納得がいかず我慢しなければならないことが出てくる可能性があります。また、完成後に不満な点が出てくるかもしれません。
外壁工事はやり直しが難しい工事です。まずは、どのような希望があるのかをしっかりと決めてから相談し、必ず100%納得のいく業者に依頼するようにしましょう。
まとめ
住宅の外壁工事には、さまざまな工法やパターン、模様があります。イメージ通りの外壁にするためにお客様の希望をはっきりと決め、業者に伝えることが大事です。
このような外観にしたい、この写真のような住まいにしたい、外壁の模様はこれがよい、どういったことでも構いません。お客様の理想をしっかり伝えることが一番のポイントです。
また、1か所だけではなくいくつかの業者に相談する方法もよいでしょう。納得のいくステキな外観となるよう、参考にしてみてください。
新着コラム
お見積り・現場調査・お問い合わせはこちら無料
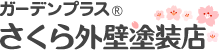
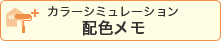



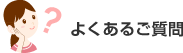











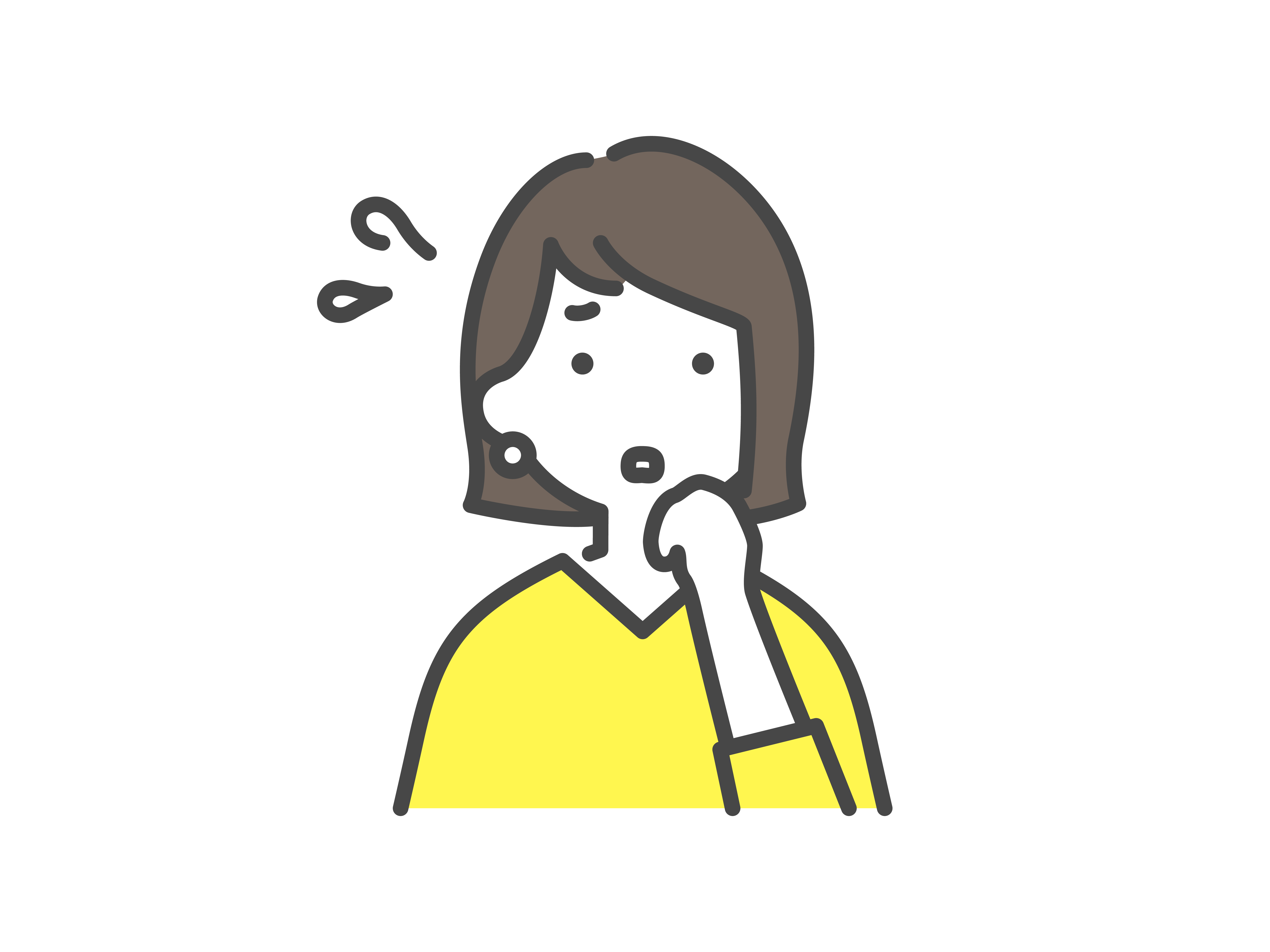


を持つ男性作業員.jpg)